昔には帰れない - You Can’t Go Back and Other Stories -
2012年に早川書房より刊行された伊藤典夫編訳/浅倉久志訳の短編集
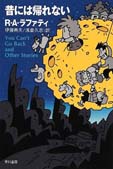
伊藤典夫編訳/浅倉久志訳・ハヤカワ文庫SF, 940円, 2012, ISBN-10: 4150118728/ISBN-13: 978-4150118723
カバーイラストレーション: 横山えいじ
2012年に日本独自編集版として、伊藤典夫編/伊藤典夫・浅倉久志共訳で刊行された。共訳としては『つぎの岩につづく』に次ぐ二冊目となる。SFマガジンなどに訳出された未収録短篇をまとめたもので、全16篇収録。新訳はなく、SFマガジンの1994年3-10月号に連載された《ラファティ・笑タイム》の未収録分など商業誌での伊藤訳をすべて収録しているが、浅倉訳の「田園の女王」「ファニーフィンガーズ」など、「種々の事情で外さざるを得なかった」という、まだ未収録の名作がいくつか残っており、つぎの短篇集につづく、が期待されますね。あとがきによると本作品集は伊藤典夫が気に入って訳した「ラファティとしてはシンプルな小品」を集めた第一部と、「ちょっとこじれているかなあ」と思われる作品と浅倉訳の長めの作品を集めた第二部で構成されている、とのこと。ちなみにあとがきは「浅倉さんのことその他」と題されており、ラファティ・ファンのみならず全SF者必読のエッセイとなっています。
なお、本短篇集は、当初は2011年に刊行が始まった新☆ハヤカワ・SF・シリーズの第1期として予告されていたが、イアン・マクドナルド「サイバラバード・デイズ」と差し替えとなりファンをヤキモキさせた。その後、ハヤカワ文庫SFでの刊行が予告され、発売日の延期はあったものの無事出版されたときはほっとしたなあ。
しかし、下記リストをみると、SFマガジンの様々な記念号に訳出されたものが多いなあ。以前は「〜記念号ならぜったいラファティ載っているよね」という期待を抱いていたものだがなあ。うん、昔には帰れないのだなあ。
収録作品:
第一部:
Eurema's Dam(素顔のユリーマ)
ラファティ唯一のヒューゴー賞受賞作(1973年)。初訳(SFマガジン 1974/10)では「愚者の楽園」のタイトルだった。世界SF大賞傑作選6(1978)収録時に「素顔のユリーマ」と改題され、ロボット・オペラ(2004)にも再録。
Other Side Of The Moon(月の裏側)
SFマガジンのラファティ追悼特集(2002.8) に訳載。
In the Garden(楽園にて)
Pine Castle(パイン・キャッスル)
SFマガジン創刊500号記念特大号Part 1 海外SF篇(1998/1)に訳載。「海外作家からのメッセージ」にはラファティも寄稿していた。
Bright Coins in Never-Ending Stream(ぴかぴかコインの湧きでる泉)
The Cliff Climbers(崖を登る)
《ラファティ・笑タイム》(1994/10)
Fall of Pebble-Stones(小石はどこから)
《ラファティ・笑タイム》(1994/3)
You Can't Go Back(昔には帰れない)
SFマガジン創刊50周年記念特大号PART・I 海外SF篇に再録された。
第二部:
Old Foot Forgot(忘れた偽足)
《ラファティ・笑タイム》(1994/9)
Golden Trabant(ゴールデン・トラバント)
SFマガジン40周年記念特大号(2000/2)の年代別SF特集2 変革の1960年代SFに訳載。居住世界シリーズ。ヴェネナトスが舞台。
And Name My Name(そして、わが名は)
《ラファティ・笑タイム》(1994/6)
All Pieces of a River Shore(大河の千の岸辺)
SFマガジンのラファティ特集(1992/4)に訳載。浅倉久志のお気に入り短篇のひとつだったが、『どろぼう熊の惑星』には版権の問題で泣く泣く収録を見送った、といういわくつきの作品。(ちょうど本作を収録した”Lafferty in Orbit”が出て間もない頃だったので許諾が得られなかったとのこと)
When All the Lands Pour Out Again(すべての陸地ふたたび溢れいづるとき)
SFマガジンのラファティ追悼特集(2002.8)に訳載。
Junkyard Thoughts(廃品置き場の裏面史)
ミステリマガジンのバカミス特集【ミステリ史を覆す! 世界バカミス宣言】(2008.6)に訳載。小山正による特集解説によれば「バカ」の意味合いは extravagant!, offbeat!, wonderful!, marvelous!, fantastic!, cool! とのこと。とすれば、ラファティらしいextravagantでoffbeatな本作を「バカミス」と認定するのに異存はないですね。Isaac Asimov's SF magazine, 1986/2初出で、このようなキャプションが添えられていた。
ラファティ氏は語る。
作家たるものはみんな、おかしな風貌であるべき。そしてすべての物語は愉快であるべき。ここ四半世紀にわたって、わたしは忠実にこの信条を守ってきたんだ。この世の中の邪悪なるものは、ほとんどがハンサムな作家の気取った作品から生じているのだからね。だけど、時々読者はわたしの作品がまったく愉快じゃないって文句をつけてくるんだ。「待てよ、待ってくれよ」私は読者に言う。「あんたは本を上下逆さまに持ってるじゃないか。さあ、もう一度試してくれ」そう、正しく持って読みさえすれば、わたしの作品は愉快なはずなんだ。この警告は特に本作を読むときにもあてはまる。まずは上下逆さまになっていないかどうか、注意することだね。さもないと、まったく訳がわからなくなってしまうだろう。
いやはや。
さあ、みなさんも一通り読み終わったら、上下逆さまにしてもう一度試してみましょう。
And Read the Flesh Between the Lines(行間からはみだすものを読め)
《ラファティ・笑タイム》(1994/8) 、アウストロと何でも知ってる男たちシリーズ。
Selenium Ghosts of the Eighteen Seventies(一八七三年のテレビドラマ)
SFマガジン創刊600号記念特大号(2006.4)に訳載。