子供たちの午後 -Among The Hairly Earthmen-
1982年に青心社より刊行された井上央編訳の短編集
2006年に新装版が刊行された
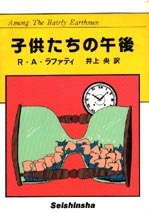

井上央編訳・Seishinsha SF Series -2001, 960円, '82, ISBN: 0097-825010-4034
カバーイラストレーション: いしいひさいち
再版:1600円, 2006, ISBN-10: 4878923237, ISBN-13: 978-4878923234
カバーイラストレーション:後藤啓介
'82に日本独自編集版として、井上央の編訳で刊行された。全作品本邦初訳。巻末には訳者による詳細な解説と作品リストがあり、未訳長篇群の内容紹介が嬉しい。発刊当時は日本で短編集は"九百人のお祖母さん"のみ刊行されていた。"Strange Doings(つぎの岩につづく)"との重複がないのは、サンリオで刊行予定だったからか?第三短編集"Does Anyone Else Have Something Further to Add?"からは4篇(アダムには三人の兄弟がいた、この世で一番忌まわしい世界、究極の被造物、奪われし者にこの地を返さん)。SFデビュー作の"氷河来たる"を含め、SFから非SFまでヴァラエティに富んだ選択がなされている。
2006年にハードカバーの新装版(旧版はソフトカバー)が刊行され、「ラファティと物語と世界」という解説が追加された。なお、「究極の被造物」「トライ・トゥ・リメンバー」「子供たちの午後」「マクグルダーの奇跡」の四編は訳文に手を入れたとのこと。
旧版の解説では、トマス・モアの大冒険、地球礁、宇宙舟歌、第四の館、イースターワインに到着、悪魔は死んだ、ローマの滅亡、炎は緑、オクラ・ハンナリ、駱駝のことを言うまでもなく、黙示録、島々の各長編について紹介があった。当時この紹介文を読んでどうしても未訳作が読みたくてしかたなくなって、そのうちネット古書店で取り寄せをはじめたのが「とりあえず、ラファティ」をはじめるきっかけのひとつとなったのだが、実際のところ完蒐した長編の大部分は積ん読状態となっているのは情けない限り。
再版で追加された解説は、主にコスキン年代記の二作目「半分しかない空」冒頭のエピソード紹介に費やされている。これは必読。
ダナ・コスキンがアムステルダムで出会った娘シェーラザードは、物語ることにより文字通り世界を作り出す。シェーラザードはダナに言う。あなたを作ったのも、わたしなのよ。そしてダナは、以前からふと感じることのあった「ニセモノ」じみた感覚、この世界はどこか不完全だという非現実感に不安を覚える。自分もまた、誰かが語った物語の不完全なキャラクターに過ぎないのではないだろうか......。
この、世界の「ニセモノ」感は、ラファティの作品に幾度となく繰り返されてきたモチーフである。このすべての世界は誰かの想像の産物にすぎないもので、どこかしら薄っぺらな感じを受けるのはそのためだってやつ。そこから、キリスト教的な解釈を踏まえて展開するラファティの物語論は、読み応えがある。訳者の井上央は大阪キリスト教短期大学教授。ふだん私なんかはよくわからないので避けている、ラファティ作品をキリスト教との関連で読み解くような論考をもっと期待してしまいますね。
収録作品:
Adam Had Three Brothers(アダムには三人の兄弟がいた)
レックビル・シリーズ。
Day of the Glacier(氷河来たる)
ラファティのSFデビュー作。Early Lafferty IIに再録されたが、編者Dan Knightからは"習作"とのコメントが。(といっても、これ以外の作品がいずれも初期作とは思えない程素晴らしいっていう流れでのコメント)
The Ultimate Creature(究極の被造物)
居住世界シリーズ。
The Pani Planet(パニの星)
Among the Hairly Earthmen(子供たちの午後)
Try to Remember(トライ・トゥ・リメンバー)
ショート・ショートもしくはコントのような軽めの作品だが、The Man Who Walked Through Cracksという凄まじい続編があり意表をつかれる。
The Polite People of Pudibundia(プディブンディアの礼儀正しい人々)
居住世界シリーズ。プディブンディアが舞台。
McGruder's Marvels(マクグルダーの奇蹟)
The Weirdest World(この世で一番忌まわしい世界)
How They Gave It Back(奪われし者にこの地を返さん)
Configuration of the North Shore(彼岸の影)
Gardner Dozois編のModern Classics of Fantasyに再録。コメントには編者好みの短編が挙げられており(火曜日の夜、われらかくシャルルマーニュを悩ませり、ブタっ腹のかあちゃん、町かどの穴、大河の千の岸辺、子供たちの午後、七日間の恐怖、つぎの岩につづく、問答無量)、収録作を含めわりと日本人の好みとあっているかも。(彼岸の影は渋めの選択だが、編者のコメントは以下の通り:最も知られておらず再録もされてない作品のひとつだが、珠玉の一品。ラファティのいいところ、すなわち素朴な豊かさ、驚くべき深みと力に満ちた歌うリリシズム、風変わりな想像力、アヴラム・デイヴィッドスンのみが張り合えるようなオフビートな衒学性の横溢、そして力強くこんがらがった無敵のユーモアのセンス、これら総てがこの作品に顕れていることを度外視したとしても)